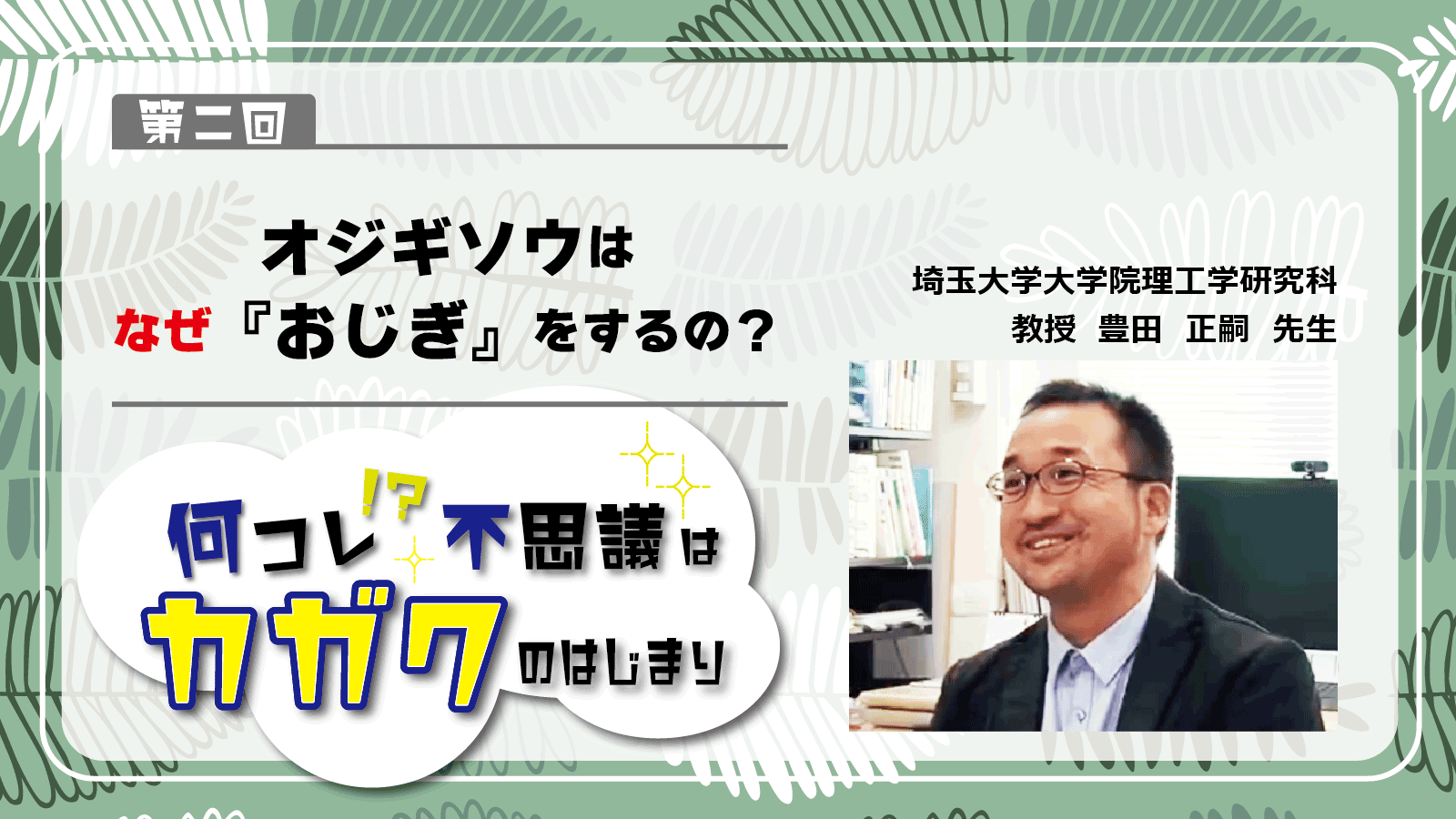何コレ不思議は“カガク”の入り口シリーズ(第1回)
豊田正嗣(とよた・まさつぐ)先生
埼玉大学大学院理工学研究科生命科学専攻分子生物学プログラム
細胞情報研究室 教授
■プロフィール
香川県出身。名古屋大学大学院医学系研究科博士課程修了。米国ウィスコンシン大学、JSTさきがけ研究者などを経て、2016年より埼玉大学大学院理工学研究科生命科学系専攻分子生物学コースにうつり、細胞情報研究室を開く。

触れると対になった小さな葉っぱが順々に閉じ、やがて葉っぱ全体が垂れ下がるマメ科植物の「オジギソウ」。まるでお辞儀をしているような動きに親しみを覚え、子どもの頃に何度も触れたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。南米原産で、世界中に帰化しているオジギソウですが、どうやって葉っぱを動かし、どんな理由でお辞儀をするのかは長らく謎のままでした。
埼玉大学大学院博士課程の萩原拓真さんと豊田正嗣先生の研究グループが、2022年にその運動の仕組みと理由を科学的に解明し、科学雑誌『Nature Communications1』に発表しました。豊田正嗣先生へのインタビュー中編では、この研究を中心にお話を伺っていきます。
カルシウムの信号が葉っぱを動かす!?
――前回のインタビューでは、「植物間のコミュニケーションは可視化できるのか?」について伺いました。今回のテーマは、「オジギソウはなぜお辞儀をするの?」です。
豊田先生 僕たちの研究室には、自由に触っていただいていいようにオジギソウの鉢を置いているのですが、考えてみると、神経も何もない植物が動くのって不思議なことですよね。動物だったら、触れられたら脳からの指令が電気信号として神経を伝わり、筋肉や関節が動くのは当然ですけど。
ところで、細胞の中のカルシウムイオンがどんな働きをしているかご存知ですか?
――細胞の中ですか? カルシウムと聞くと、真っ先に「骨」が浮かびます。

豊田先生 カルシウムイオンは、骨や歯以外に私たちの体を形作っている細胞にも含まれていて、例えば、脳からの電気信号を神経経由で筋肉に伝える時に使われています。膝や肘を曲げるなど筋肉が収縮する時は細胞の中のカルシウムイオンが引き金となりますし、内分泌系にも関与しています。
――カルシウムにそんな大事な役割があるとは知りませんでした。
豊田先生 そこで本題です。まず、オジギソウの動きも動物同様にカルシウムイオンが影響しているのでは?と仮定し、遺伝子組み換え技術を使って体内のカルシウムイオンの濃度が上がると蛍光タンパク質が光るオジギソウを作りました。さらに、カルシウムイオンの移動の様子を可視化できる蛍光イメージングシステムも作りまして。
――実験装置から作られたんですか!? 生物物理学だけでなく、機械工学的にも高度な知識がないと、なしえなかった実験ですね。
豊田先生 僕は長らく、自分だけの装置を作って、自分にしかみられない世界を見てきました。とはいえ、装置開発は企業と連携することもありますし、手作りする時もイチから作るのではなく、既成の部品を買ってきて自分で組んだりしているんですよ。
――それにしてもすごいです。
豊田先生 もちろん、さまざまな知識は必要ですが。それに、皆さんは携帯のカメラで富士山や月を撮るじゃないですか。顕微鏡もカメラのようなものなのになぜ大きなものが撮れないかと言うと、試料を複雑な光学系で構成された長い筒で覗く形が視野を決めてしまっているからです。だけど、その形ではオジギソウの体内で何が起きているかを観察するには不向きな訳です。ないなら作ればいい訳で、三脚に高感度カメラと一眼レフカメラ用レンズを取り付けた形の装置を作り、対象を横から観察できるようにしました。

ちなみに、オジギソウがなぜお辞儀をするかは昔から研究の対象でしたが、僕と院生たちとで150年分ぐらい遡って250余りの論文にあたっても、それを科学的に証明した論文はひとつもありませんでした。そこで、それをする意味があるかどうかは分からないけれど、科学的に証明したいと思ったんです。
――150年間、封印されていた謎を先生たちのチームが解き明かしたことになりますね。
豊田先生 ピンセットでオジギソウの葉の先端を触れた時に、葉の付け根にある葉枕と呼ばれる運動器官のカルシウム濃度が高くなって光り、そのシグナルが次々と伝わって、葉が順々に閉じていくのがわかりますよね。
オジギソウは触れられたり、傷つけられたりすると、カルシウムシグナルが葉脈を伝わり、葉枕の細胞内のカルシウム濃度が高くなって葉が閉じ、やがて葉っぱ全体がお辞儀をするように垂れ下がります。
――映像でみると一目瞭然ですね。
葉の先端に触れると、葉枕で細胞内のカルシウム濃度が上昇し、次々に葉の運動が起こる。
(埼玉大学 豊田 正嗣 教授よりご提供)
健気で強いオジギソウの生存戦略
豊田先生 なぜオジギソウは葉を閉じるのかを調べるために、CRISPR/Cas9と呼ばれるゲノム編集技術を使って、茎や葉の付け根にある葉沈と呼ばれる器官の運動細胞をなくし、お辞儀をしないオジギソウも作りました。人間で言うと、腕はあるけれど関節や筋肉がないみたいな感じです。そうしたオジギソウと普通のオジギソウを何十組と比較することで、生理学的な違いが見えてくるのではと考えたんです。
今度はみんなにバッタを捕ってきてもらい、用意した2種のオジギソウ(お辞儀するオジギソウとお辞儀をしないオジギソウ)のうち、どちらの葉っぱがより食べられるかの実験を行いました。すると、”お辞儀をしない”方の鉢が40%ぐらい食べられたのに対し、”お辞儀をする”方の鉢の食害は20%程度にとどまりました。カルシウムの信号を止める薬を吸わせたオジギソウでも実験してみたのですが、そちらも40%ぐらいの葉がバッタに食べられました。そこで、オジギソウが葉っぱを閉じるのは防御のためと分かったんです1。
――葉が閉じると、バッタは驚いて飛んでいってしまうのでしょうか?
豊田先生 僕も実験前はそう思っていましたが、バッタは葉が閉じること自体にはそれほど驚いていない様子でした。どうやら閉じた葉っぱに足が挟まれるようで、食べにくいからかどこかへ行ってしまう。足場をなくして食べられないようにするのかと考えると、植物って健気ですよね。 ちなみに、オジギソウの体内にはミモシンと呼ばれる毒性の成分が含まれています。ある程度育つと水平方向にどんどん成長するし、バラのような鋭いトゲも生えてくるので、海外では嫌われていたりします。オジギソウには可愛らしいイメージがありますが、物理的に動くし、間接的にも攻撃してくるしで、なかなか強い植物なんです。
閉じないハエトリソウの生存戦略とは?
豊田先生 次に見ていただきたい映像があります。その前に、ピンセットでハエトリソウの葉に触れてみてください。
――触れると葉っぱが閉じるんでしたっけ。あれ、閉じませんね。
豊田先生 では、30秒ほど待ってから、もう一度同じ葉に触れてみてください。
――また閉じませんね。
豊田先生 閉じると思っていた葉が閉じない。なぜか? 種明かしをしましょう。ハエトリソウは湿地帯に生息する食虫植物ですが、間隔を開けて触れると閉じないのは大事な生存戦略なんです。ハエトリソウの葉は、一度閉じると次に開くのに時間がかかるのと、エネルギーを使うのとで、3回ぐらい空振りすると枯れてしまいます。ですから、たまたまゴミがついたなどの空振りを避け、しっかり虫を捉えた時にのみ葉を閉じたい訳です。ハエトリソウの向き合った葉の中には、感覚毛と呼ばれるセンサーのような小さな毛が生えています。もし、葉の中に虫がいれば、動き回って複数回その毛に触れるはずで、それが確実視されると葉が閉じます。では、感覚毛に触れた後、葉が変化していく映像を見てもらいましょう。

ピンセットで1回触っただけでは閉じず、時間をおいてもう一度触ると葉を閉じた。
――葉っぱ全体にカルシウムが広がってゆくのが分かります。
豊田先生 感覚毛に触れると蛍光が一瞬で広がりますが、もう一度触れるとさらに蛍光が明るく広がり、ある閾値を超えると葉が閉じることがお分かりいただけたかと思います。ところが、1回目と2回目の刺激の間隔がだいたい30秒以上あくと葉は閉じません。つまり、ハエトリソウに脳はないけれど、確実に獲物が中にいるかどうかを刺激回数と時間で把握しているんです。これを、同じラボの須田啓さんが解き明かしました2。
――ハエトリソウ賢い……。それもこれも、イメージング技術があったからこそ分かったことですね。過程で何が起きているかが鮮明になったことで、植物がより身近に感じられました。それに、ここで明らかになったことが、さらに先の展開を生む予感がします。
豊田先生 ちょっと話は変わりますが、遠心顕微鏡ってご存知ですか? 顕微鏡そのものが高速回転するんですけど、先にカメラがついていて、カメラで捉えた映像は、リアルタイムで無線で外に飛ばせるんです。細胞を遠心させて、分離している最中に細胞の中で何が起きているかを見るためのもので、これらの独自の装置が評価されて、最近、学会で賞をいただいたばかりです。この遠心顕微鏡によって、植物の重力感知のメカニズムの一部が明らかとなりました3。
――地球とは異なる重力下で、植物がどんな動きを見せるのかが分かれば、食糧難の時代の宇宙プラントなどに繋がっていきそうです。
豊田先生 生き物って色々な素子が集まったシステムじゃないですか。ですから僕たちは、そのシステムを見ていこうと思って、日夜研究を続けています。もちろん、生化学のように生き物の構成物質を観察・測定することも大切ですし、2014年には「今まで見れなかったミクロなものが見れるようになった」として、顕微鏡の性能を劇的に向上させた研究者がノーベル賞を受賞しました。それでも僕らはマクロでいく。研究者は、自分が信じるものがあるのであれば、大きな潮流に乗りすぎない方がいいかもしれません。
――これから研究者を目指す学生や、若い研究者に響く言葉ではないでしょうか。次回のインタビューでは、豊田先生の子供時代のお話や、どんな紆余曲折を経て、現在の道を進んでこられたかについてお伺いしていきたいと思います。お楽しみに!
■掲載論文情報
- Hagihara T, Mano H, Miura T, Hasebe M, Toyota M (2022)
Calcium-mediated rapid movements defend against herbivorous insects in Mimosa pudica. Nature Communications 13: 6412 - Suda H, Mano H, Toyota M, Fukushima K, Mimura T, Tsutsui I, Hedrich R, Tamada Y, Hasebe M (2020)
Calcium dynamics during trap closure visualized in transgenic Venus flytrap. Nature Plants 6, 1219–1224 - Toyota M, Ikeda N, Sawai-Toyota S, Kato T, Gilroy S, Tasaka M, Morita MT (2013)
Amyloplast displacement is necessary for gravisensing in Arabidopsis shoots asrevealed by a centrifuge microscope.Plant Journal76:648-660.
掲載元:Lab. First
関連記事
植物間のコミュニケーションは可視化できるの? |何これ⁉不思議はカガクのはじまり(第1回)
埼玉大学大学院理工学研究科生命科学専攻分子生物学プログラム 豊田 正嗣 先生